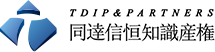
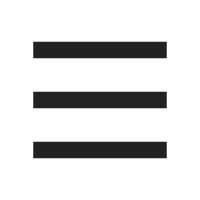

探したいことを検索する

一般的には、特許権の保護範囲とは、特許権の法律的効力が及ぶ発明創造の範囲のことを指している。中国特許法第59条第1項の規定により、発明又は実用新案の特許権の保護範囲はその請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の解釈に用いられることができる。以上から分かるように、一方では、特許請求の範囲は、特許権の保護範囲を確定するためのものであり、特許制度において極めて重要な地位を占めている。他方では、発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、請求項の解釈とは密接に関係している。
特許制度が正常に動くように確保するために、特許権者のために確実で効果ある法律的保護を提供する必要があるほか、公衆が既存技術を利用する自由を有するように確保する必要もある。そのため、どのような行為を施したら他者の特許権を侵害することとなるかを公衆が明確に理解できるように、特許独占権の範囲を定める法律文書が必要となる。特許請求の範囲は、上記目的を達成するために定められる特殊の法律文書であり、特許権の付与並びに特許権の保護には重要な意義を有するものである。つまり、特許請求の範囲というものを通じて、どのような技術が特許保護の対象となるものであるかを公衆が十分に理解できるようになっている。よって、特許請求の範囲の最も重要な役割として、特許権の保護範囲を確定することである。即ち、それにより、どのような技術案が特許保護の対象となるものであるかを社会公衆及び司法機関が判断しやすくなっている。請求項を読むことによれば、その簡潔な文言から特許権の保護範囲を容易に理解することができる。
しかしながら、特許請求の範囲という法律文書があるからといって、全ての問題が解決できたということではない。保護対象となる技術案を簡潔な文言で表現することは簡単ではなく、如何なる状況においても理想的な結果が得られるとは限らない。特許請求の範囲に係わる発明は文言で限定され、即ち、発明や実用新案の創造構想を文言で表現するため、文言そのものの不確定性と、思案が正確に表現できないという面とにより、文言で限定される技術案の保護範囲が不明確であたっり確定できなかったりするという状況は避けられない。出願人としても、創造構想に含まれる全ての均等の技術案が文言の形で確定することが難しい。ある場合では、機能又は効果特徴で請求項を限定することも許される。特許請求の範囲をなす文言に基づき明確な保護範囲が得られるとは限らない。それにより、特許請求の範囲を如何にして見るか、如何にしてその役割を奏するかという問題が出てくる。それについて、早い時期に特許制度を実行し始める国も長期にわたって探索してきた。探索の焦点として、特許権者のために効果ある保護を提供することと、社会公衆のために十分な法律確定性を提供することとの間にきちんとバランスが取れるようにすることにある。
特許制度の実行経過において、歴史上の各時期では、それぞれの国が特許権の保護範囲の確定方法について異なるやり方を試みてきた。一般的には、歴史上で三つの代表的なやり方があると思われる。一つ目は、英米を代表とする「周辺限定制」、二つ目は、ドイツを代表とする「中心限定制」、三つ目は、「折衷制」というやり方である。
「周辺限定制」については、当該原則によれば、特許権の保護範囲が特許請求の範囲のみにより認定される。即ち、厳格的に特許請求の範囲の文言に基づき解釈しなければならない。特許請求の範囲に記載された範囲は、特許保護の対象となる最大限である。それに基づき、特許請求の範囲を厳格的に解釈しなければならず、特許権の保護範囲は特許請求の範囲における請求項の範囲を超えてはならず、特許請求の範囲に含まれていない内容は特許権の保護範囲には入らない。特許権者は、当該範囲内で権利を行使しなければならない。特許請求の範囲が不明瞭であったり不明確であったりする場合に限って、明細書と図面に基づく特許権の保護範囲に対する限定解釈が適用される。当該原則を採用する主な国として、イギリス、アメリカ等の国が挙げられる。
「中心限定制」については、当該原則によれば、請求項の文言で表現される範囲は、特許権の保護対象となる最小範囲である。特許権の保護範囲は、特許請求の範囲の記載を中心と根拠とするとともに、ある程度で拡張してもよい。即ち、特許権の保護範囲が特許請求の範囲を中心とすると認定される一方、特許請求の範囲の記載に拘らずに、当該発明創造の性質や目的も考慮に入れ、明細書と図面の内容を参照しながら発明創造の構想全般を全体的に理解し、中心以外の一定の範囲内の技術も特許保護の範囲内に入れる必要もある。当業者が明細書と図面を分析して含まれてよいと考える技術であれば、特許権の保護範囲に入るものである。当該原則を採用する主な国として、ドイツ等の大陸法系の国が挙げられる。
「周辺限定制」と「中心限定制」という二つの学説の長所と欠点が互いに補足しあっている。前者は、社会公衆に対する特許権の保護範囲の確定性を確保することには有利であるが、融通がきかないため、請求項の作成があまりにも重要すぎたことになり、例え少しのミスでも取り返しのないこととなり、特許権者のために効果ある法律保護を提供することができなくなる。一方、後者の長所として、その保護範囲の拡張性が高く、柔軟性のあることであり、特許権者には有利である。しかしながら、融通が利きすぎてしまうと、必要な法律確定性の保証には有利ではなく、安定的な経済秩序の構築には有利ではなく、公衆にとっては公平性が足りない。
「周辺限定制」と「中心限定制」とは、いずれもある面では不足があるため、「中間道」としての「折衷制」が現れてきた。「折衷制」という原則は、「周辺限定」原則と「中心限定」原則との折衷である。当該原則によれば、特許権の保護範囲は主に特許請求の範囲の記載に基づき認定され、特許請求の範囲の記述に不明点や不明確なところがある場合、明細書と図面に基づき特許請求の範囲を解釈することもできる。当該原則を採用する主な国として、「欧州特許条約」の加盟国である。このように、「折衷制」により、特許権の保護範囲を確定する際に、請求項の内容に準ずる原則に従いながら、明細書と図面に基づき請求項を解釈するという折衷的解釈をする原則も結びつけている。こうして、特許の保護範囲と請求項の文字記載の保護範囲とはまったく一致しなければならず、請求項には不明確なところがある場合に限って明細書と図面に基づきそれらを明確にするという「周辺限定」原則の採用が避けられるし、その一方、請求項の総括的な発明中核だけを確定して、その保護範囲としては、当業者が明細書と図面を分析してから特許権者の保護請求している範囲に属すると認定する範囲まで拡張することができるという「中心限定」原則の採用も避けられる。折衷的解釈は「周辺限定制」と「中心限定制」との中間にあるものであり、それにより、特許権者に対する合理的で正当な保護と、公衆に対する法律安定性及びその合理的な利益とが結びつけられている。
特許権の保護範囲と請求項の解釈について、中国の特許法としても「折衷制」原則を採用している。つまり、明細書と図面に基づき請求項を合理的に解釈できるということが受け入れられている。合理的に解釈するということにより、ある範囲内で解釈できるようになるが、どこまで解釈できるか、具体的な実務で如何にして確定するかは、具体的な状況に応じて確定する必要がある。請求項に対する解釈は「請求項に準ずる」という規定に従わなければならないことから、請求項の内容に従わずに解釈してはいけず、請求項の内容を解釈する際にその範囲を拡張しすぎたり、上位概念の内容を明細書のある具体的な実施例に絞るという縮小解釈をしたりすることは、「請求項に準ずる」という立法趣旨に背いている。
明細書と図面に基づき請求項を解釈することで特許権の保護範囲を確定する際に、さらに均等の原則と禁反言の原則という二つの重要な原則も結びつけることが注意されたい。
均等の原則は、主に請求項の文言で表現される保護範囲に対する拡張解釈に用いられる。「均等」とは、被告人の侵害者により実施される技術案が、特許の請求項に係る技術案と比べると、一つ又は一部の技術的特徴で相違しているが、対応する技術的特徴がほぼ同様な方法でほぼ同様な機能を達成させ、ほぼ同様な効果を生じる場合、特許権の保護範囲に入り、特許権を侵害する行為をなすことである。
禁反言の原則は、主に請求項の文言で表現される保護範囲に対する限定解釈に用いられる。均等の原則は、請求項の保護範囲を均等の技術案まで拡張し、ある程度では特許権者の利益を拡大している。禁反言の原則は、均等の原則を限定するものであり、社会公衆の利益を守ることができる。特許権者が、特許出願及び特許無効審査の際に、請求項の範囲について特許行政機関に主張した内容は、その権利の範囲を確定する根拠とされるべきである。つまり、特許権者が、従来技術に対する旧請求項の新規性欠如又は進歩性欠如の欠陥を克服するために一旦あきらめた範囲は、権利侵害判定時に、解釈することで再び均等の保護範囲に入れてはいけない。禁反言の原則は、信義誠実の原則の具体的な表れであり、特許権者が反言して請求項の保護範囲を勝手に拡張したり縮小したりすることで、公衆の利益を損なうことを防止することができる。
以上で述べたように、発明又は実用新案の特許権の保護範囲が請求項の内容により特定されるが、ある場合では、請求項の内容を解釈する際に明細書と図面も参照する必要がある。よって、発明又は実用新案の特許権の保護範囲と請求項の解釈とは密接に関係している。請求項の内容を解釈する際に、均等の原則と禁反言の原則との適用も注意されたい。つまり、請求項を正確に解釈することは、複数の方法を総合的に適用する結果である。このようにしてこそ、特許権者のために効果ある保護と、社会公衆のために十分な法律確定性との関係をうまく扱うことができる。

TDIP&Partnersが北京科学技術博覧会のテーマフォーラムに参加
2025-05-09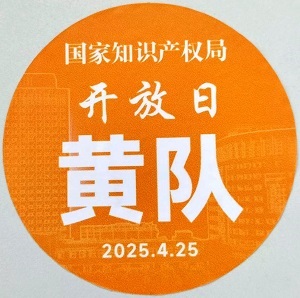
2025年全国知的財産権教育週間オープンデーに参加しました
2025-04-25
TDIP&PARTNERSが代理した5件の特許が第24回中国特許賞を受賞
2023-04-24